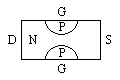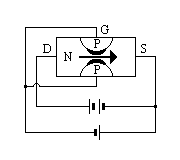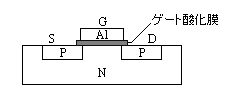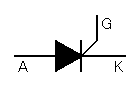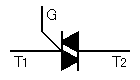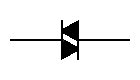トランジスタは小さな電流で大きな電流を制御する、電流−電流動作と呼ばれる仕組みで動作しますが、FETはトランジスタとは異なり電圧で電流を制御する、電圧−電流動作をします。これはトランジスタが発明される以前に増幅器として使われていた真空管と同じ動作です。そもそもトランジスタが開発途上だったとき、研究者らはFETのような素子を作ろうとしていました。ところが偶然にもできたのはトランジスタだったというわけです。FETはトランジスタが開発された後に登場しました。
では前口上はこれぐらいにして、まず接合型と呼ばれるFETの構造を見てみましょう。
ここで、Gはゲート、Sはソース、Dはドレインと呼びます。Gはこの図では2カ所ありますが、実際には内部で接続されて1本の端子となって外部に出ています。
さて、ではFETの図記号を見てみましょう。
これは接合型のNチャネルと呼ばれるFETの図記号です。Pチャネルの場合は矢印が逆方向になります。この図記号で分かるかもしれませんが、FETの端子はそれぞれ、ゲートがベースに、ソースがエミッタに、ドレインがコレクタに対応しています。
それでは、接合型FETの動作原理を見てみましょう。
Gになにもつないでいない場合、D-S間には電流が流れます。なぜなら、DとSとはN形シリコンで直接つながっているからです。ところがG-S間に逆バイアスをかけると、
このように、PN接合のところに空乏層ができます(図の黒い部分)。すると、DからSに流れようとする電流(実際にはSからDに向かう電子の流れですが)がこの空乏層に通路を狭められるので、流れにくくなります。これはG-S間の逆バイアス電圧を上げるとより顕著になります。つまり、G-S間の逆バイアスのかけ方で、D-S間を流れる電流の制御が出来る、要するに増幅作用があるわけです。
ここで気を付けて欲しいのは、通常はD-S間は導通していて、G-S間に逆バイアスをかけて初めて、電流が制限されるということです。トランジスタでは、B-E間に電流を流さない限り、C-E間に電流は流れませんでしたよね?ここがトランジスタと接合型FETの違うところです。そしてこのようなFETをデプレッション形と呼びます。FETの中にはトランジスタと同じように、G-S間に逆バイアスをかけて初めてD-S間に電流が流れるものもあり、このようなFETはエンハンスメント形と呼ばれています。
FETがトランジスタに比べて優れているのは、G-S間は逆バイアスで制御しているという点です。逆バイアスは電流が流れないとダイオードの所で解説したように、G-S間には電流が流れないわけです。実際にはすこしだけ漏れ電流というものが流れますが、それでもトランジスタに比べればかなり省エネです。
FETには接合型のほかにMOS型と呼ばれるものもあります。MOSとはMetal Oxide Semiconductorの頭文字を取ったものです。MOS FETではゲート端子が、ゲート酸化膜という二酸化シリコン(要するに石英ガラスです)で出来た膜を隔てて付けられています。ではPチャネルMOS FETの構造を見てみましょう。
この図でAlと書いてあるのはアルミの事です。これがゲート端子になっています。このMOS FETの動作原理は以下の通りです。通常D-S間はPN接合のために導通していませんが、Gからゲート酸化膜を隔ててマイナスの電圧を加えると(つまりGに−、Sに+)ゲート酸化膜の底の部分に、N形シリコン中の正孔が引き寄せられ、D-S間に正孔で出来た細い道が形成されます。するとこれが電流の通り道となり、D-S間が導通するわけです。これは先ほどのFETの分類で言うと、エンハンスメント形になります。
MOS FETが優れているのは、ゲート端子がゲート酸化膜によって電気的に絶縁されていることです。つまり全くと言っていいほど電流が流れないわけです。ただしこのゲート酸化膜は薄く、さらに絶縁されていると言うことは入力インピーダンスが高い(絶縁状態なので、抵抗値が高いと考えてください)ので、静電気が加わるとこの酸化膜が破壊されてしまいます。ですからお店でMOS FETを購入したときには、導電性スポンジ等に差した状態で手渡してくれると思います。
ここまでFETの話をずっとしてきましたが、実際にはFETそのものを使うよりも、MOS FETで構成されたC-MOS ICを使う機会の方がはるかに多いと思います。その場合にも静電気で壊れやすいという特徴は変わらないので、注意してください。
4−5.サイリスタ
ここから先の話は、いわばおまけです。実際にこれらの部品を使う機会はあんまりないと思いますが、知識として知っておいて損はないと思うので、解説しておきます。
サイリスタはトランジスタにさらにもう一つPN接合を付けた、PNPNの4層からなる素子です。図記号は次の通りです。
この図のAはアノードでPNPNの左端のPに、Kはカソードで右端のNに、そしてGはゲートで、真ん中のPにそれぞれつながっています。動作原理は次の通りです。まずA-K間は通常導通していません。なぜなら途中NからPには導通しないからです。しかし、Gに+、Kに−の電圧を加えると、AからKに電流が流れるようになります。そしてこれはG-K間の電圧を止めても続きます。つまりG-K間に短時間でも電圧をかければ、AからKにはずっと電流が流れ続けるわけです。トランジスタならベース電流を止めればすぐにC-E間の電流が流れなくなりましたから、ここがトランジスタとサイリスタの違うところです。A-K間の導通状態をストップさせるにはA-K間の電流自体を止めるか、A-K間を逆バイアス状態にしなければなりません。
サイリスタはGに電圧を加えることでA-K間を導通(ON)させることは出来ますが、逆にOFFにすることはできません。これがサイリスタの弱点です。この弱点を改良したものに、GTOサイリスタがあります。GTOとはGate Turn Offの頭文字を取ったもので、Gに電圧を加えることでA-K間をON出来るのは一緒ですが、Gに−、Kに+の電圧(つまり逆バイアス)を加えることでOFFにすることもできるようになっています。GTOサイリスタは、インバータ制御式の電車に多用されています。
ところで、サイリスタは別名SCRとも呼びます。SCRとはSilicon Controlled Rectifier(シリコン制御整流素子)の頭文字を取ったもので、これは米GE社によって商標登録されています。サイリスタはどこの会社か忘れましたが、別の会社の呼称です。
(2003/02/19追記:サイリスタは米RCA社の呼称です)
4−6.トライアック・ダイアック
トライアックは、サイリスタを交流でも使用できるようにしたものです。互いに逆方向になるように2つのサイリスタを接続してあります。Gにパルスを加えることで、T1-T2間が導通します。また、ダイアックは互いに逆方向になるように2つのダイオードを接続したものです。ダイアックは印加された交流電圧が、ある値を超えると鋭いインパルスを生じます。これをトライアックのゲートに加えることで、交流電流の制御をすることができます。なおダイアックには、半導体の中では珍しく極性がありません。どちらの向きに使ってもOKです。トライアック、ダイアックはセットで、特に調光器や、交流モーターの回転数制御などに使われています。図記号は以下の通りです。ダイオードの記号が互いに逆方向になるような図記号になっているのが分かると思います。トライアックについてもっと詳しく知りたい方は、こちらのページが参考になるかと思います。
トライアック ダイアック
なお、トライアック、ダイアックはそれぞれTRIAC、DIACと書きます。TRIACのTRIとは3、つまり端子が3つあることを表し、ACは交流のACを表しています。同じくDIACのDIとはダイオード(DIODE)のDIと同じで端子が2つあることを表し、ACは同じく交流のことです。実際の製品については、たとえばRSコンポーネンツで購入することができます。
4−7.IGBT・その他
近年、パワーデバイスの発展はめざましく、特にサイリスタなどは自己消弧(ゲート端子の制御でOFF状態にすること)が出来ないため、活躍の場を奪われつつあります。代わって使われるようになったのが、GTOサイリスタやパワーMOS FET、IGBTなどです。パワーMOS FETは、MOS FETを並列に数万個程度接続して電力を得るようにしたもので、モーター制御等に多用されるようになっています。IGBTはInsulated Gate Bipolar Transistor(絶縁ゲートを持つバイポーラトランジスタ)の頭文字を取ったもので、構造的にはMOS FETで電力用バイポーラトランジスタ(要するに普通のトランジスタ)を制御するようになっています。このため入力インピーダンスが高く、大電力を制御するのに向いていますが、MOS FETよりもスピード面では劣ります。まあ、IGBTは実際に使う機会は無いと思いますが、パワーMOS FETはモーターの制御で使うこともあるでしょう。